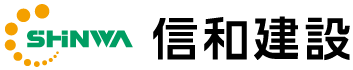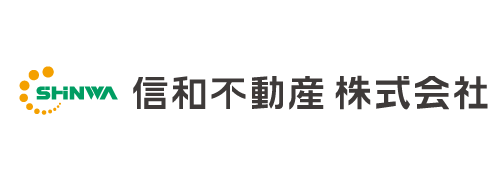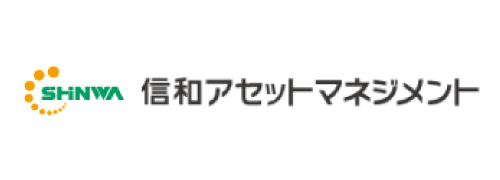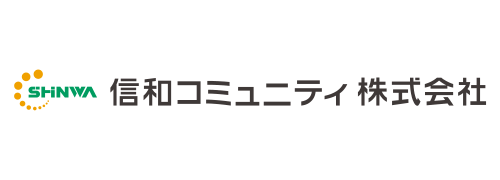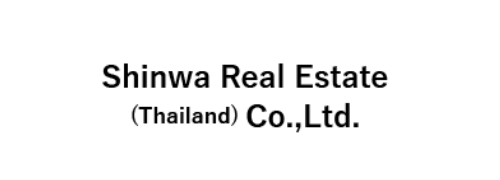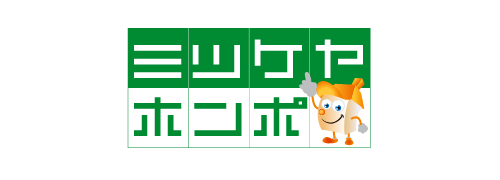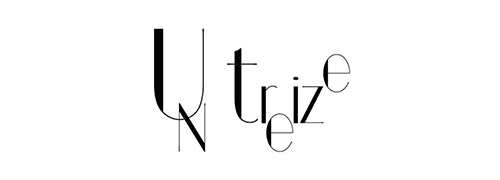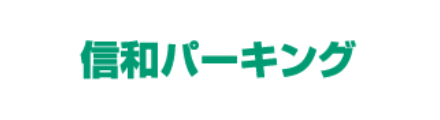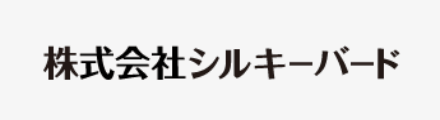遺言書作成のポイント
どなたであっても、ご自身の相続に当たっては円満な資産承継を願うものだと思いますが、それを実現する方法の一つとして遺言書の作成が考えられます。
遺言書の作成に当たっては、いくつか抑えておきたいポイントがありますので、以下でそれをご紹介します。
1.全ての財産を網羅的に記載する
例えば、「この土地は確実に長男に遺したい」というお考えがある場合、その部分だけを遺言書として作成することは可能です。特定の財産を確実に承継して税金の特例(農地や自社株の納税猶予など)の適用を予定するような場合は、当該財産についてだけでも遺言書を作成しておくことは有効だと思います。
しかし、それ以外の財産は相続人間で遺産分割協議が必要となるため、遺言書を作成するのであれば全ての財産を網羅的に記載することをお勧めします。
なお、遺言書を作成してから相続が発生するまでの間に財産内容が変動する可能性も考慮して、「遺言書に記載した財産以外の財産については、〇〇に相続させる」という記載をしておけば、財産内容に変動があっても対応することができ、後に遺言書を書き換える必要がなくなります。
2.「相続させる」と「遺贈する」
相続人に対して財産を承継する場合は、「相続させる」と記載します。
また、遺言書によって、相続人以外の方に財産を承継することもできますが、その場合は「遺贈する」と記載します。
<参考①:遺言書で配偶者居住権を設定する場合>
自宅について「配偶者居住権」を設定する場合、相続人間での遺産分割協議で配偶者が取得する方法と、遺言書に記載することで配偶者が取得する方法が考えられますが、遺言書に記載する場合は「遺贈する」と記載する必要があります。
<参考②:農地がある場合>
農地について所有権を移転する場合は農地法3条の許可申請を行う必要がありますが、相続人が相続で取得する場合はこの手続は不要です。
一方で、農地を相続人以外の方に承継する場合は、遺言書で「遺贈する」と記載する必要があり、この場合は農地法3条の許可申請が必要となります。3条許可には農地の面積などの要件があるため、遺言書に記載したからといって必ずしもそれが実現するとは限りません。相続人以外の方に農地を承継したい場合には、3条許可の要件を満たすかどうかの事前確認が必要となります。
3.予備的な遺言
「この財産を〇〇に相続させる」と記載した対象の相続人がご高齢である場合、遺言者よりも先に亡くなってしまうことも想定しておく必要があります。その後に遺言書を書き換えることができれば良いのですが、書き換えができなければ遺言書の該当部分の記載は無効となり、当該財産については相続人間での遺産分割協議が必要になります。
このような場合は、「〇〇が遺言者よりも先に死亡していたときは、〇〇に相続させるとした財産は△△に相続させる」と記載しておくことで、遺産分割協議や遺言書を書き換える手間を省くことができます。
4.遺留分に配慮する
兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の取り分として民法で保障された「遺留分」があります。子がいない夫婦のように、相続人である兄弟姉妹に遺留分がない場合は、「全財産を妻に相続させる」という遺言書があればそのとおりに財産を承継することができますが、遺留分のある相続人がいる場合、例えば「全財産を長男に相続させる」というような極端な財産配分を行うと他の相続人から遺留分の請求を受けかねず、遺言書を作成したことでかえって円満な資産承継を妨げることになってしまうかもしれません。
とはいえ、全ての相続人の遺留分を満たす財産配分は困難な場合もあると思いますし、関係が疎遠な場合は、遺留分相当額の財産でさえ渡したくないというお考えもあり得ます。そのような場合は、遺留分に相当する金額が減少するような対策を講じるのも一つかもしれません。
<対策例①:養子縁組>
相続税の計算においては、何人と養子縁組を行ったとしても、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人と養子の数に制限があります。
しかし、法定相続分を規定する民法においては養子の数に制限はありません。したがって、養子の数が増えた分、一人一人の遺留分は減少することになります。ただ、むやみに養子縁組を行うことはかえって揉める要因にもなりかねないため、手続自体は簡単なものですが、実行に当たっては慎重な判断が必要です。
<対策例②:保険の活用>
例えば父親が亡くなり、受取人である長男が父親の死亡に伴う生命保険金を受け取ったとします。この場合の生命保険金は、長男が父親から相続により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。(法定相続人の人数×500万円までは相続税は非課税。)
一方、民法においては受取人固有の財産であるとして、生命保険金は遺留分の計算対象である財産には含まれません。よって、預貯金や有価証券などの金融資産を生命保険に組み替えることで、相続税の軽減効果は非課税枠を超える分には得られないものの、遺留分の計算対象となる財産額が減少する効果は期待できます。
ただし、例えば財産の大半を生命保険に組み替えるなど、保険金受取人である相続人とその他の相続人との間に生ずる不公平が著しいと判断されれば、生命保険金も遺留分の計算対象に組み込まれる可能性がある点については注意が必要です。(平成16年10月29日最高裁判決)
また、遺留分相当額を渡す前提で、生命保険金の受取人に当該相続人を指定しているケースがあります。争いにならなければこの方法でも構いませんが、保険金は受取人固有の財産なので、相続財産に対して別途遺留分の請求をされてしまう可能性が残ります。もし遺留分を請求されるようなことがあれば、必ず金銭での請求となるため、請求された相続人はその対処が必要になってしまいます。
このような場合は、財産を中心的に相続する方(子A)を保険金の受取人とし、子Aから子Bに代償金として遺留分相当額を支払う内容の遺言書を作成しておくことで、遺留分の請求を受けないようにする工夫が考えられます。
5.一次相続と二次相続の合計相続税を考える
配偶者には配偶者の税額軽減の適用があるため、法定相続分に相当する金額または1億6,000万円のいずれか大きい金額までは、財産を相続しても相続税はかかりません。しかし、配偶者が多額の財産を相続すると、配偶者の固有財産の多寡やご年齢・健康状態にもよりますが、二次相続における相続税の負担は増加する可能性があります。
よって、一次相続と二次相続を合わせた合計の相続税を意識して、一次相続における配偶者の取得割合を検討する必要があります。
一次相続の相続財産が5億円、配偶者の固有財産が5,000万円、子は3人と仮定すると、一次相続では配偶者の取得割合を50%以上とすれば相続税の負担は最も少なくなります。しかし、二次相続までの間に財産の増減がないと仮定すれば、配偶者の取得割合が高くなるほど、二次相続時の相続税は増加し、トータルの相続税も増加することになります。
一つの目安としては、一次相続における配偶者の取得割合を30%程度とすることがトータルの相続税負担を最も抑えることができるイメージです。
なお、二次相続までの間に相続税対策を講じることができる場合は、一次相続では配偶者の取得割合を高めて配偶者の税額軽減を最大限活用し、二次相続の対策により二次相続の際の相続税負担も抑えるというプランも考えられます。
|
トータル 相続税額 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
一次想続での 取得割合 |
一次相続 | 二次相続 | ||||
| 配偶者負担 | 子負担 | 一次合計 | 子負担 | |||
|
配偶者の取得割合 (一次相続) |
100% | 59,624,820 | 0 | 59,624,800 | 125,949,600 | 185,574,400 |
| 90% | 47,699,800 | 11.924.900 | 59,624,700 | 110,719,200 | 170,343,900 | |
| 80% | 35,774,900 | 23,849,900 | 59,624,800 | 95,490,000 | 155,114,800 | |
| 70% | 23,849,900 | 35,774,900 | 59,624,800 | 80,259,600 | 139,884,400 | |
| 60% | 11,924,900 | 47,699,800 | 59,624,700 | 66,021,900 | 125,646,600 | |
| 50% | 0 | 59,624,800 | 59,624,800 | 54,600,000 | 114,224,800 | |
| 40% | 0 | 71,549,800 | 71,549,800 | 39,599,700 | 111,149,500 | |
| 30% | 0 | 83,474,700 | 83,474,700 | 24,599,400 | 108,074,100 | |
| 20% | 0 | 95,399,700 | 95,399,700 | 14,400,000 | 109,799,700 | |
| 10% | 0 | 107,324,700 | 107,324,700 | 6,299,700 | 113,624,400 | |
| 0% | 0 | 119,249,700 | 119,249,700 | 199,800 | 119,449,500 | |
一次相続で配偶者が相続する財産としては、ご自宅や金融資産が考えられます。ご自宅の敷地は、配偶者が取得すれば小規模宅地等の特例を適用することができ、面積330㎡を上限に土地の評価額が80%減額されます。
また、金融資産は残された配偶者の生活資金としても必要であることと、消費や贈与を行いやすいため、二次相続に向けた対策を取りやすいという利点が考えられます。
6.おわりに
遺言書は作成する方(遺言者)が自由にその内容を決めることができますが、単に作成すれば良いというものではなく、しっかりと内容を検討して円満な資産承継につながるものにすることで初めてその効用が得られるものだと思います。
作成に当たっては専門家にも相談しつつ、お元気なうちに実行に移すことをお勧めします。
【情報提供元:税理士法人 FP総合研究所】
https://www.fp-soken.or.jp/